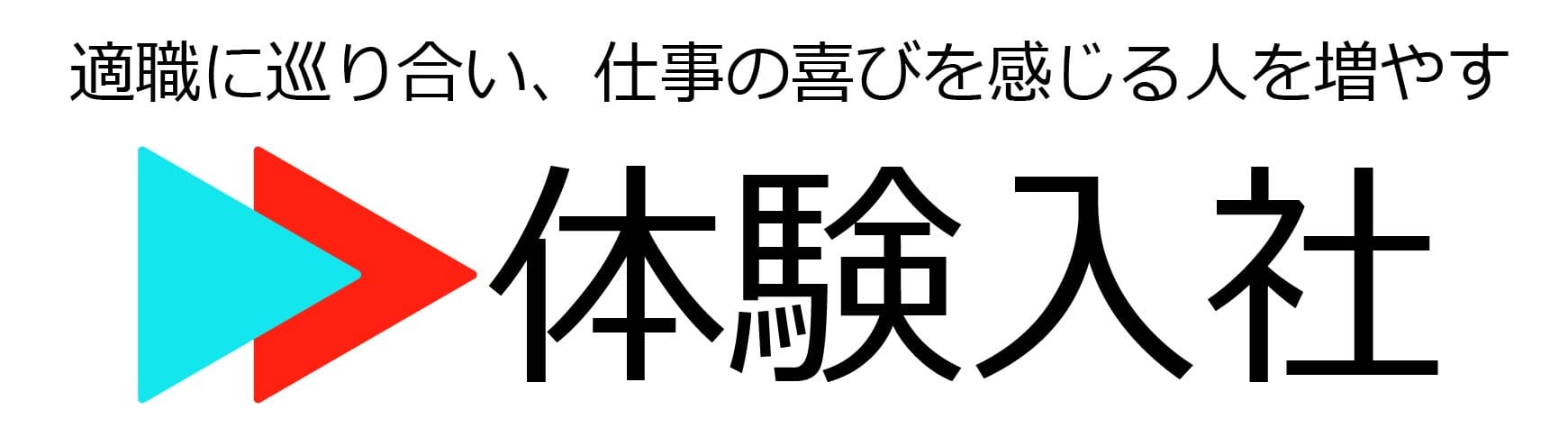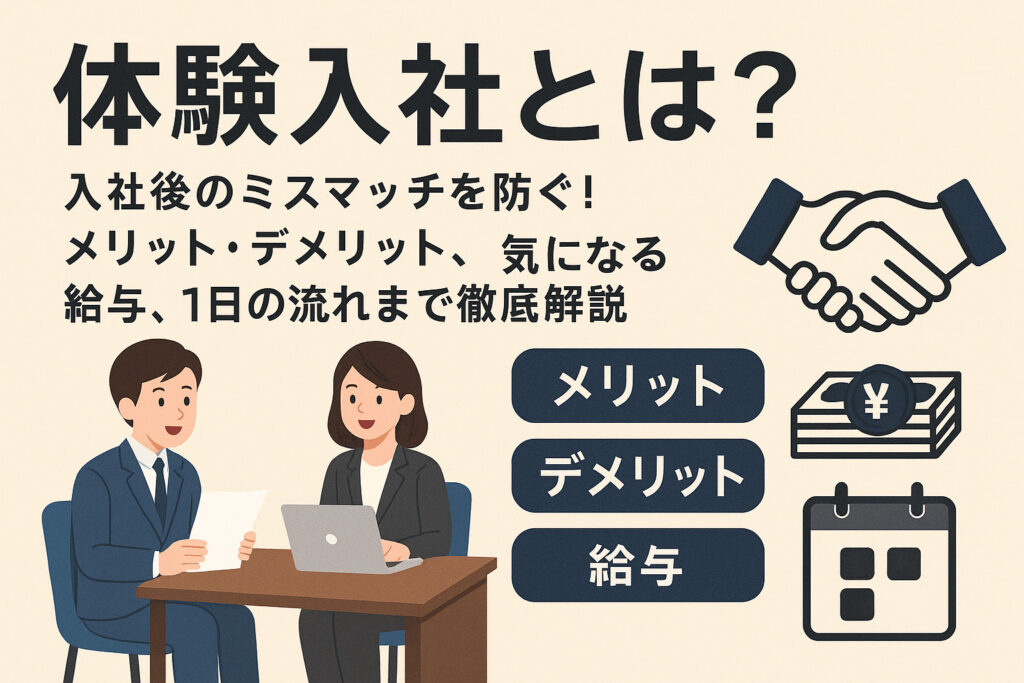
転職活動において、「スキルは合うと思ったのに、なんだか社風が合わなかった」「面接では魅力的だったのに、入社してみたらギャップがあって…」なんて不安を感じたことはありませんか?
こうした入社後の「こんなはずじゃなかった」は、働く私たちにとっても、採用する企業にとっても、とても残念なことですよね。
(実際、厚生労働省の調査では、新卒で入社した方の約3割が3年以内に離職しているというデータもあり、企業側も「採用のミスマッチ」や「早期離職」には頭を悩ませています。)
そんな、お互いにとってのミスマッチを防ぐための方法として、今、「体験入社」が注目を集めています。
この記事では、体験入社とは何か、その基本的なところからインターンシップとの違い、参加するメリットや気になる点、お給料は出るのか、当日の流れ、そして導入している企業の事例まで、わかりやすく解説していきます。
体験入社とは?

まずは、体験入社の基本的な考え方と、なぜ今この方法が選ばれているのかを見ていきましょう。
体験入社の定義
体験入社とは、採用選考プロセスの一部として、候補者(あなた)が企業で実際に短期間(半日から数日間)働いてみることを言います。
多くの場合、一次・二次面接を通過して、最終面接の前や内定(または内々定)を出す前のタイミングで「よかったら、うちの会社で一度働いてみませんか?」と企業側からお誘いがあることが多いです。
実際の職場で、入社後に担当するかもしれないお仕事に近い業務をこなしてみたり、チームになるかもしれないメンバーとコミュニケーションを取ったりします。
今までの「面接」が、過去の経験や考え方をもとにした「お話」が中心だったのに対して、体験入社は、実際の業務や職場環境という「リアル」な場での「行動」を通じて、お互いの理解を深めていく選考方法なんです。
導入が進む背景
体験入社が広まっている背景には、主に3つの理由があると考えられます。
- 転職・採用ミスマッチの深刻化
従来の面接や履歴書だけでは、私たちが持つ本当のスキルや、カルチャーフィット(企業文化との相性)を見極めるのには、どうしても限界がありますよね。特に、コミュニケーションの取り方や、問題解決の進め方といった「実際に働いてみないとわからない」部分でのすれ違いが、早期離職の原因になっているんです。
- 働き手の価値観の変化
終身雇用が当たり前でなくなった今、特に優秀な方ほど「自分に合う環境かな?」「このチームで成長できるかな?」と、しっかり見極めたいと思っています。私たち働き手側も、入社した後の「こんなはずじゃなかった」を避けるため、企業のリアルな情報を求めているんですね。体験入社は、その透明性を感じられる方法として、候補者からも選ばれ始めているんです。
- 「ジョブ型雇用」への移行
年功序列の「メンバーシップ型」から、お仕事の内容をはっきり決める「ジョブ型」へ移る企業が増える中で、「そのお仕事を本当に任せられるか」を具体的に見極める必要が出てきました。体験入社は、求人票に書かれた通りのスキルを持っているかを判断する上で、とても役立つ方法なんですね。
体験入社の基本的な流れ(参加する場合)
もしあなたが体験入社に参加することになった場合、以下のような流れで進みます。
- 応募・選考:
まずは、興味のある企業に応募し、通常の書類選考や一次面接などを受けます。 - 体験入社の提案:
選考が進んだ段階(例:二次面接に合格した後)で、企業から「体験入社をしてみませんか?」と半日から数日間の体験入社の提案があります。
※事前に選考プロセスに体験入社の実施が明示されているパターンが多いです。 - 条件の確認:
実施する日時、期間(例:1日、3日間)、実施内容、そして「報酬や交通費は出るのか?」といった点を事前にしっかり確認しましょう。 - 体験入社の実施:
当日は、オリエンテーション(当日の流れ、使うツールの説明など)を受けた後、実際の業務に取り組んだり、チームメンバーとランチに行ったりします。 - フィードバック:
実施した後、企業側から「働いてみてどうでしたか?」と感想を聞かれたり、逆に現場チームからのフィードバック(「こんなところが良かったですよ」など)をもらったりします。 - 合否の連絡:
面接での評価と、体験入社での様子(スキルが合うか、社風が合うか)を総合的に見て、最終的な合否の連絡が来ます。
インターンシップとの違い
体験入社とよく似ていて間違えやすいのが「インターンシップ」です。でも、この二つは似ているようで、目的も対象も違います。
対象者の違い
- インターンシップ:
メインの対象は「学生さん(新卒・既卒)」です。特に、就職活動を控えた大学3年生などを対象に、キャリアについて考えてもらうことや、企業のことを早めに知ってもらうことを目的にしています。 - 体験入社:
メインの対象は「中途採用の候補者(転職を考えている方)」です。すでにお仕事の経験を持つプロフェッショナルな方や、第二新卒の方などが対象になります。
実施内容の違い
- インターンシップ:
期間は1日のセミナー形式から数ヶ月に及ぶ長期のものまで様々です。内容は、グループワーク、職場見学、社員との座談会など、「職業体験」や「教育」といった側面が強いのが特徴です。 - 体験入社:
期間は半日から数日程度と短めです。内容は、入社後に実際に行う「実務」そのもの、またはそれに限りなく近い課題に取り組みます。例えば、営業同行・営業ロープレ、研修体験 、ミーティング(打ち合わせ)の参加、メンバーとのランチ会、など、より実践的なのが特徴です。
評価・位置づけの違い
- インターンシップ:
(特に短期の場合)評価が必ずしも採用に直結するわけではありません。あくまで「会社のことを知ってもらう」のがメインの目的であることも多いです。 - 体験入社:
「採用選考プロセスの一部」として、はっきり位置づけられています。実施した結果(パフォーマンスやフィット感)が、合否を決めるための大切な材料になります。
|
比較項目 |
体験入社 |
インターンシップ |
|
主な対象 |
中途採用候補者(転職者) |
学生(新卒) |
|
目的 |
採用のミスマッチ防止(選考) |
キャリア教育、企業ブランディング |
|
実施時期 |
選考プロセス中盤から終盤 |
就職活動本格化前 |
|
実施内容 |
実務、リアルな業務 |
グループワーク、職場見学、教育 |
|
評価 |
合否判断に直結 |
採用に直結しない場合も多い |
気になるギモン:体験入社で賃金・給与はもらえるの?

「体験入社って、お給料は出るの?」これは、すごく気になるところですよね。
結論から言うと、「労働者」に該当する場合は、賃金・給与が発生します。
では、どんな場合に「労働者」になるのでしょうか? 法律(労働基準法)では、主に2つのポイントで判断されます。
- 企業の「指揮命令関係」があるか(例:時間や場所を管理され、具体的な業務の指示を受けている)
- 作業によって得られた利益・効果が、企業のものになるか(例:作った資料がそのまま営業で使われる)
【具体的な例】
- 賃金が発生しないことが多いケース:
- 見学がメインの場合
- 簡単な業務体験(教育的な意味合いが強く、企業の利益に直結しないもの)
- 賃金が発生する可能性が高いケース:
- 成果物(顧客リストの作成、記事の執筆、プログラム作成など)の提出があり、その成果が企業の利益になる場合
実際には、半日から1日体験入社や職場見学は、労働者とはみなされず、賃金が発生しない(または交通費や日当のみの)ケースが多いです。
一方で、長期のリモート体験入社などで、実務をしっかりこなす場合は、労働者とみなされて賃金が発生することが多くなります。
ここは後でトラブルにならないよう、体験入社に参加する前に、企業側に「報酬や交通費は出ますか?」としっかり確認しておくことが大切です。
体験入社のメリットとデメリット(気になる点)
体験入社は、私たち候補者にとっても、企業にとっても、良い面と気になる面があります。まずは、私たち候補者側の視点から見てみましょう。
体験入社のメリット(あなたが得られること)
- ミスマッチの回避(最大のメリット):
求人票や面接官の話だけではわからない、「職場のリアルな雰囲気」「チームのコミュニケーション(チャットのやり取りの速さ、会議の進め方)」「上司になるかもしれない人のマネジメントスタイル」などを肌で感じ取ることができます。 - スキルの客観的証明:
面接でお話しするのが苦手でも、実務スキルに自信がある人にとっては絶好のアピールチャンスになります。「話す」んじゃなくて「実行する」ことで、自分の能力をしっかり評価してもらえます。 - 入社後の不安解消:
「このチームでやっていけるかな…」という不安を、入社する前にスッキリ解消できます。これにより、入社を決断するときの迷いがなくなり、気持ちよくスタートを切れるようになります。
体験入社のデメリット(気をつけること)
- 時間的拘束:
特に今のお仕事で働きながら転職活動をしている人にとって、平日の日中に「1日」の時間を確保するのは、かなり高いハードルになってしまいます。有給休暇を取ってもらう必要が出てきますよね。 - 精神的負担:
「試されている」という状況下で働くことは、いつも以上にプレッシャーやストレスがかかってしまうものです。 - 不採用時のダメージ:
1日かけて時間と労力をかけたにもかかわらず不採用となった場合、普通の面接でのお見送りよりも、ショックが大きく感じてしまうかもしれません。
【企業側は?】体験入社を実施する企業のメリット
(ちなみに、企業側にはこんなメリットがあるんですよ。)
- ミスマッチ防止と早期離職の削減:
これが企業側の一番のメリットです。スキル(能力)とカルチャー(社風)の両方が本当に合うかを「事実」で確認できるので、入社後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、定着率アップにつなげたいと考えています。 - リアルなフィードバックがもらえる:
たとえ入社につながらなくても、体験してくれた候補者からの「オンボーディングの段取りが良くなかった」「チームの雰囲気が思ったより静かだった」といった「本音」は、企業が職場環境を良くしていくための貴重なヒントになります。 - 会社の魅力を直接伝えられる:
「うちの会社は、中を見せても大丈夫ですよ」という透明性を見せることで、候補者の信頼を得たいと思っています。また、優秀なチームメンバーと働いてもらうこと自体が、強力な「魅力づけ」になると考えています。
【企業側は?】導入で気をつけていること
(もちろん、企業側もこんな点に気をつけて準備しているんです。)
- 受け入れ準備(工数):
候補者に有意義な時間を過ごしてもらうため、当日の業務設計、サポートするメンター社員の手配、PCやアカウントの準備など、現場の社員もしっかり時間をかけて準備しています。 - 賃金・契約ルールの整備:
先ほどの「お給料は出るの?」の部分ですね。候補者に「労働」とみなされる業務をしてもらう場合は、法律を守るために、短期アルバイト契約を結んだり、報酬をきちんと支払ったりするルールを、社労士や弁護士と相談しながら整備しています。
体験入社を有意義にするための2つの心構え

では、もし体験入社に参加することになったら、どんなことに気をつければいいでしょうか?
単なる「見学」で終わらせず、お互いにとって有意義な時間にするために、2つの心構えをおすすめします。
- 体験入社の「目的」をはっきりさせる
ただ参加するだけではもったいない!「今日はこれを絶対に確認するぞ」という目的を持って行くことが大切です。
例えば、こんな目的が考えられます。
- 「働いている人たちや、社風は自分と合いそうか?」
- 「お仕事内容は、自分の強みを活かせそうか?」
- 「残業や休日などの働き方は、希望する条件と合いそうか?」
- 「今のお仕事と比べて、本当に転職するべきか?」
目的を明確にさせて、当日にしっかり確かめましょう!
- 企業側もあなたを見ている、という意識を持つ
あなたが企業を確かめているのと同じように、企業側もあなたのことを見ています。
では、企業はどんなところを見ているのでしょうか?
- カルチャーフィット(一緒に働くメンバーや、社風と合いそうか)
- スキルフィット (お仕事内容は合っているか、能力を活かせそうか)
- 入社意欲(積極的に質問しているか、楽しそうに取り組んでいるか など)
「見られている」と意識しすぎると緊張してしまいますが、「お互いに相性を見極める場なんだ」という意識で、ぜひ積極的にコミュニケーションを取ってみてくださいね。
1日体験入社のスケジュール例
では、実際にどんなことをするのか、営業職とエンジニア職のスケジュール例を紹介させていただきますね!
【営業職のスケジュール例】
- 10:00 採用担当者より1日の流れ説明、オフィス説明
- 10:30 体験入社をするチームでの紹介・挨拶
- 11:00 営業チームミーティングの見学
- 12:00 チームメンバーとランチ
- 13:00 営業同行や営業ロールプレイングの見学・体験
- 16:00 採用担当者より感想のお伺い
- 17:00 終了
【エンジニア職のスケジュール例】
- 10:00 採用担当者より1日の流れ説明、オフィス説明
- 10:30 体験入社をするチームでの紹介・挨拶
- 11:00 開発チームミーティングの見学
- 12:00 チームメンバーとランチ
- 13:00 メンバーとペアプログラミング・コードリーディング体験
- 15:00 デザイナー職、ビジネス職メンバーとの交流
- 16:00 採用担当者より感想のお伺い
- 17:00 終了
◆Retty株式会社の1日体験入社スケジュール例◆
『従業員数が100名を超えても、Rettyが体験入社を続ける理由とは?』より
- 10時 一日の流れを説明、オフィス案内
採用担当より説明、案内をさせていただきます。 - 11時 入社後、働く可能性のあるチームで体験入社開始
マネージャーより体験入社される方の紹介をさせていただきます。その後、メンバーとのコミュニケーションを取っていただきます。 - 12時 メンバーとランチ
Rettyに掲載されているおすすめのお店でランチです。お互い自然体で技術の話や興味のあることを話します。 - 13時 メンバーとペアプログラミング・コードリーディング
GitHubのアカウントを付与します。入社後、一緒に働く可能性のあるメンバーと行います。 - 15時 ミーティング・ディスカッションに参加
改善ミーティング・競合サービス調査ミーティングに参加いただき、意見も出していただきます。 - 17時 三次面接
役員や代表取締役による面接です。体験入社と同日に行うことがあります。 - 18時 終了!
▼実際の体験入社事例
https://media.taikennyusha.com/taikennyusha-case/9993/
体験入社だけじゃない? いろいろな選考方法

企業は、体験入社が「今、どんな動きができるか」や「社風に合うか」を見るのに適していると考える一方で、それだけではわからない部分を、他の選考方法と組み合わせて、お互いの理解を深めようとしています。
- (参考)企業が体験入社と組み合わせる他の選考
- 構造化面接:
面接官の好みで評価がブレないよう、「過去にこんな場面でどう行動しましたか?」といった質問(STAR面接など)をあらかじめ決め、評価基準を統一している面接です。 - リファレンスチェック:
あなたの同意のもとで、前の職場(または今の職場)の同僚や上司に、あなたの働きぶりについてヒアリングする方法です。面接や体験入社では見えなかった「第三者からの客観的な評価」も参考にしたい、という意図があります。 - アセスメントツール:
適性検査(SPI、玉手箱など)やスキルテスト(コーディングテストなど)を組み合わせ、あなたの考え方のクセや、基礎的なスキルレベルを事前に確認することもあります。
- 構造化面接:
- 体験入社の経験は、入社後にも活かされます
体験入社は、「採用したら終わり」ではないんです。
もし、あなたがその会社に入社することになったら、体験入社でわかった「あなたの得意なこと」や「ちょっと苦手そうなこと(例:このツールに慣れていなかったな)」といった情報は、入社後のサポート(オンボーディング)に活かされます。
入社初日から、あなたがスムーズに活躍できるように、企業側も研修プログラムなどを工夫してくれるんですね。
導入企業の成功事例から学ぶ!
体験入社は、特にIT・Web業界の先進的な企業で、積極的に取り入れられていますね。どんな企業がやっているのか、少しのぞいてみましょう。
(※このセクションは、一般的に公開されている情報に基づき、各社の取り組みの傾向を解説するものです。)
- Chatwork株式会社
ビジネスチャットツールを提供するChatwork社は、「トライアウト」と呼ばれる体験入社制度を導入していることで知られています。特にエンジニア採用において、選考の最終段階で1日(または複数日)のトライアウトを実施。実際のチームに入り、実務に近い課題に取り組むことで、スキルの見極めと同時に、同社のバリュー(価値観)とフィットするかをお互いに確認しています。
https://media.taikennyusha.com/taikennyusha-case/9815/ - Retty株式会社
実名口コミのグルメサービスを運営するRetty社も、体験入社を大切にしています。同社は「User Happy(ユーザーハッピー)」という価値観を非常に大切にしており、面接での対話だけでは測れない「カルチャーフィット」を、実際の業務やチームメンバーとの交流を通じて判断しています。1日から数日間の有償での実施が基本とされています。
https://media.taikennyusha.com/taikennyusha-case/9993/ - hey株式会社
「STORES」などのサービスを提供するhey社(旧:Coiney、ストアーズ・ドット・ジェーピー)は、「おためし入社」という名前で体験入社を導入しています。選考プロセスの中で、候補者と企業の双方が「もっと知りたい」と感じた場合に実施されます。報酬を支払い、実務に近い課題に取り組むことで、「入社後の後悔」をゼロにすることを目指しています。
https://media.taikennyusha.com/taikennyusha-case/9849/ - アジアクエスト株式会社
DX支援などを行うアジアクエスト社も、中途採用において「体験入社制度」を導入しています。同社の場合は、内定承諾後の「オファー面談」と入社日の間に、入社意思を固めるための「最終確認」として実施するケースもあるようです。入社後の配属先チームで業務を体験することで、入社後のスムーズな立ち上がりと不安解消をサポートしています。
https://media.taikennyusha.com/taikennyusha-case/10567/
ミスマッチ防止を加速させる新潮流 ― 「体験入社動画」とは?
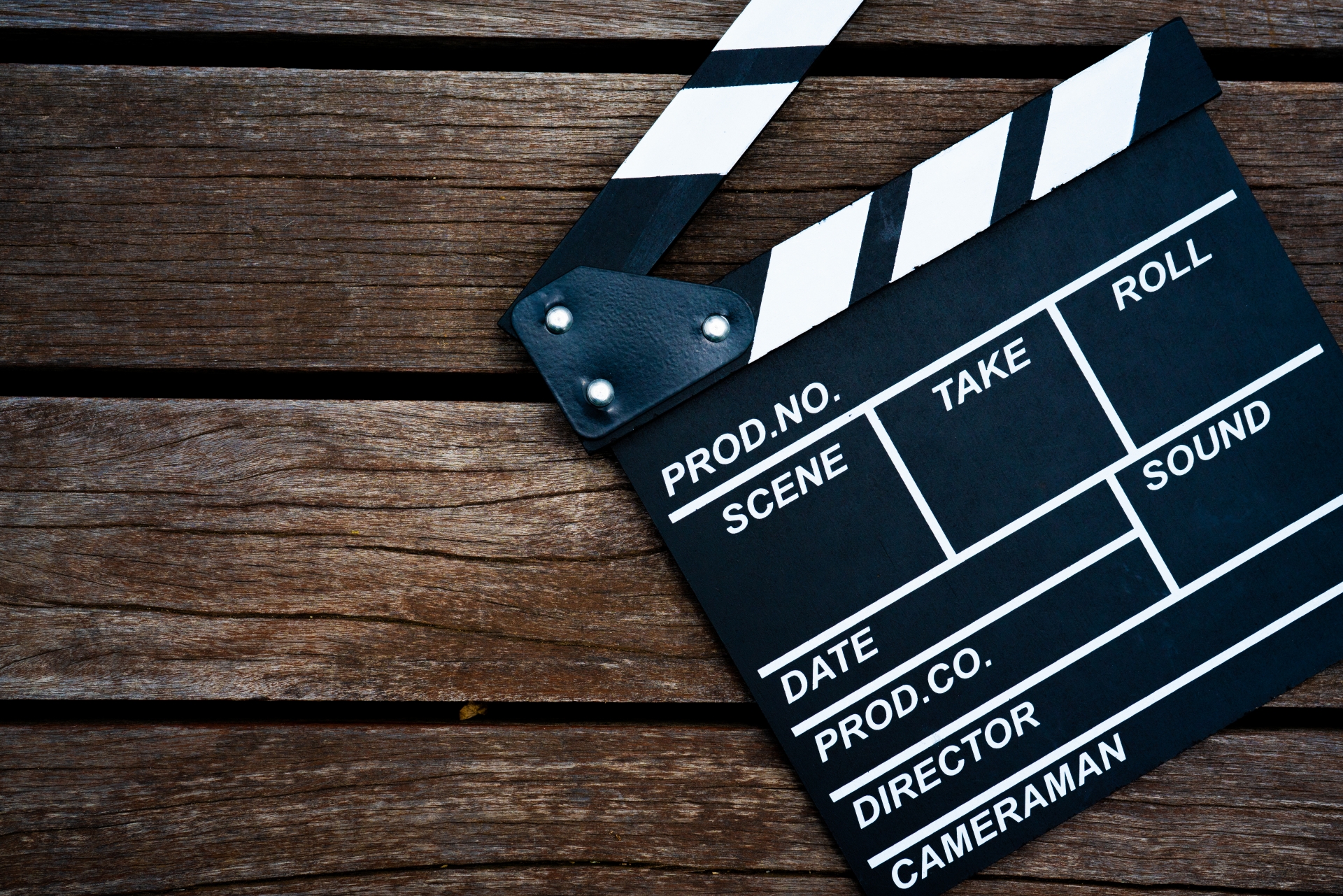
ここまで解説してきた「実際に会社に行く体験入社」は、効果が高い反面、「参加するための時間を確保するのが大変」「企業側の受け入れ準備も大変」という課題がありました。特に、今の仕事が忙しい優秀な人ほど、体験入社に参加できない…というジレンマですよね。
この課題を解決する新しい方法として「体験入社動画」という考え方が注目されているんです。
AI×動画で仕事のリアルを伝える『体験入社』
これは、従来の「おしゃれなPR動画」や「社員インタビュー動画」とは、ちょっと一味違うものなんです。
特定のサービス(ここでは仮に『体験入社』サービスと呼びます)では、AIなどを活用して企業の文化や業務内容を詳しく分析し、その上で、私たち候補者があたかも「1日バーサルで働いた」かのような没入感のある動画コンテンツを作成します。
内容は、「実際の会議の様子(リアルな議論)」「トラブル発生時のチャットのやり取り」「上司からのフィードバック風景」など、企業の「良い面」も「大変な面」も包み隠さず見せる(シミュレーションする)点に特徴があります。
『体験入社動画』のメリットは?
「体験入社動画」は、実際に会社に行く体験入社の課題をデジタルの力で解決してくれます。
- 候補者側のメリット(いつでもどこでも体験できる):
私たちは、今のお仕事の合間や自宅で、時間や場所を選ばずに「バーチャル体験」ができます。これにより、「忙しくて体験入社には行けないけど、リアルな雰囲気は知りたい」というニーズに応えてくれます。 - 企業側のメリット(たくさんの人に届けられる):
実際の体験入社は1対1でしか実施できませんが、動画は一度作ってしまえば、何百人、何千人の候補者にも「バーチャルな体験入社」を提供することができます。 - お互いのミスマッチを事前に防げる:
リアルな動画を見た候補者が「この働き方は自分には合わないな」と感じれば、選考の早い段階で辞退する判断ができます。これは企業にとっても「ミスマッチを事前に防げる」ということであり、面接にかかるお互いの工数を減らすことにも繋がるんですね。
関連サービス
この領域では、AIを活用した「体験入社動画」サービス以外にも、オンラインで仕事の疑似体験を提供する「ジョブシミュレーション」ツールや、社員のリアルな一日を切り取ることに特化した採用動画サービス(例:moovyなど)が登場しており、採用のデジタル化をサポートしています。
まとめ ― 納得のいく転職のために「体験入社」を活用しよう
転職でのミスマッチや、「こんなはずじゃなかった」という早期離職は、私たちにとっても、企業にとっても、本当に残念なことです。
従来の面接だけではわからない「本当の相性」を、入社する前に確かめられる「体験入社」は、私たちが納得してキャリアを選ぶための、とても強力な味方になってくれます。
もちろん、参加するには時間もかかりますし、緊張もするかもしれません。でも、それ以上に「この会社で働きたい!」と心から思える会社に出会えたり、逆に「ちょっと違うかも」と入社前に気づけたりする、大きなメリットがあります。
もし選考を受けている企業があれば「体験入社は可能ですか?」と聞いてみたり、まずは「体験入社動画」のようなサービスで、いろんな会社のリアルをのぞいてみたりすることから、新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。