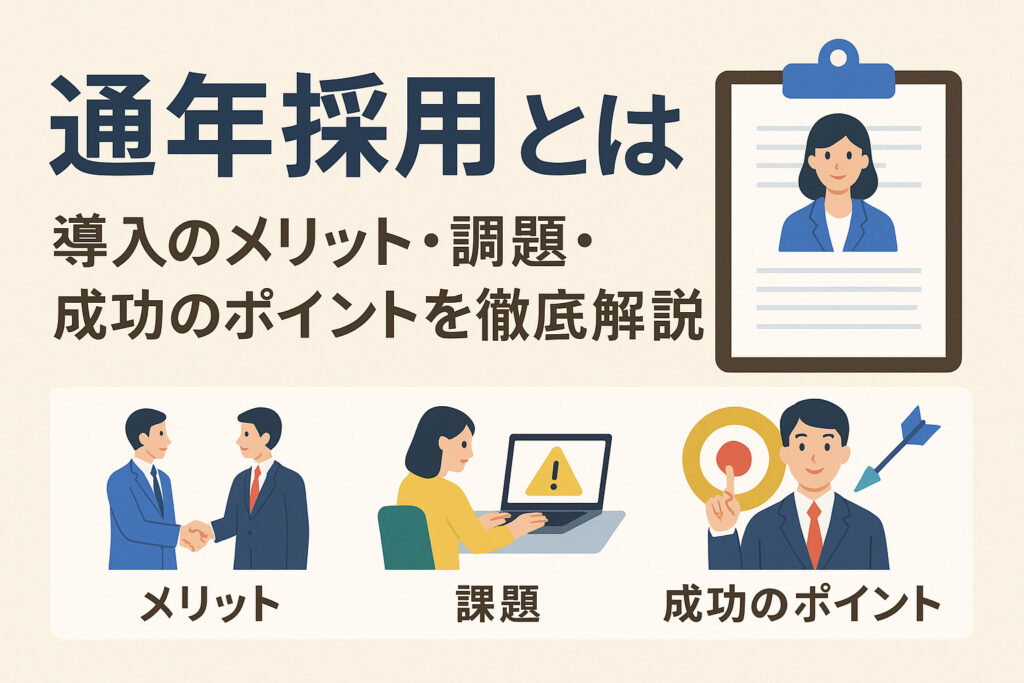
「通年採用を始めたいが、何から手をつければいいかわからない」
「新卒・中途の垣根をなくし、柔軟な採用をしたい」
人材獲得競争が激化する中で、いま多くの企業が注目しているのが 通年採用(year-round recruitment) です。
従来の“新卒一括採用”に代わり、企業の成長スピードや多様な働き方に対応できる新しい採用スタイルとして広がりを見せています。
この記事では、通年採用の概要からメリット・デメリット、導入の進め方、成功企業の事例までを詳しく解説します。
通年採用とは?定義と目的を整理

通年採用とは、時期を限定せずに年間を通じて人材を採用する仕組みを指します。
「4月入社」「新卒一括」などのスケジュールに縛られず、
事業の成長や人材ニーズに応じて柔軟に採用できるのが特徴です。
背景
- 少子高齢化による人材不足の加速
- 若手人材の転職・ジョブチェンジ志向の高まり
- 即戦力・専門人材の採用ニーズの拡大
- 海外大学・国内外MBA卒など、グローバル人材の多様化
- リモートワーク普及に伴う「採用の地理的制約」からの解放
つまり、通年採用は “採用を柔軟にし、経営と連動させる仕組み” です。
単なる採用時期の変更ではなく、企業の人材戦略そのものを変える取り組みといえます。
通年採用の主な種類と形式
通年採用といっても、実施形態は企業によって異なります。
ここでは代表的な3つの形を紹介します。
① 完全通年採用型
年間を通じて常時エントリーを受け付け、選考・採用を行うモデル。
大手グローバル企業や外資系に多く、採用活動と人材育成が一体化しています。
特徴
- 時期に関係なく人材を採用
- 必要なタイミングで採用ポジションを開設
- 定期的にオンボーディングや研修を実施
② ハイブリッド型
新卒一括採用を継続しながら、一部職種や中途採用を通年で実施するモデル。
国内企業では最も多い形式です。
特徴
- 基本は春入社を中心にしつつ、追加募集を通年実施
- 欠員補充・新規事業向けに柔軟対応が可能
- 採用コストを抑えつつ母集団を確保
③ 期間限定型(随時採用)
一部期間に採用枠を設ける方式。
「上半期/下半期採用」「四半期ごとの選考」など、年間を複数サイクルに分けて実施します。
特徴
- 採用業務を管理しやすい
- 新卒・第二新卒をターゲットにしやすい
- 採用リソースを分散できる
通年採用が注目される理由
1. 労働市場の変化
転職やジョブチェンジが一般化し、「いつでもキャリアを見直す」時代になりました。
企業もこの流れに合わせ、**“求職者が動くタイミングで採用できる”**仕組みを求めるようになっています。
2. 人材獲得競争の激化
限られた採用時期に集中すると、他社との競争が激しくなり、優秀層の採用難度が上昇します。
通年採用は“ピーク時の競争を避け、確実に口説く”戦略として有効です。
3. DX・新規事業推進による即戦力需要
デジタル人材・エンジニア・企画職など、即戦力の中途採用を年間通じて行う必要があります。
「必要な時に採れる体制」が企業競争力を左右します。
4. 採用ブランディングの一環
通年採用を実施する企業は、“オープンで柔軟な企業文化”という印象を与えやすく、
採用ブランディングの強化にも繋がります。
通年採用のメリット

メリット①:優秀人材を逃さない
募集タイミングを限定しないことで、良い人材に出会ったときに即採用できる。
「採用機会の最大化」が最大の利点です。
メリット②:採用スピードの向上
採用フローを年間通じて運用することで、
承認・面接・内定プロセスを標準化・効率化できます。
メリット③:採用コストの平準化
ピーク期の広告費・人材紹介費が分散され、年間での採用コストを最適化できます。
メリット④:多様な人材プール形成
新卒・中途・第二新卒・地方・海外など、異なる背景を持つ人材を継続的に集められます。
メリット⑤:柔軟な入社スケジュール
事業フェーズやプロジェクト進行に合わせて入社時期を調整でき、
現場の人員計画と採用計画を一致させやすくなります。
通年採用のデメリット・課題
課題①:採用体制への負荷
年間を通して選考を行うため、人事部門の稼働が増加。
採用担当者のリソース確保と、ATS(採用管理システム)の整備が必須です。
課題②:育成・受け入れの難しさ
新卒一括採用では研修・配属が一斉に行われるのに対し、
通年採用では入社時期がバラバラのため、教育・オンボーディングの仕組みが必要です。
課題③:採用広報の継続コスト
常に候補者へ情報発信を行う必要があるため、
採用サイト・SNS・動画などを継続的に更新するリソースが求められます。
成功する通年採用のポイント5つ
① 採用計画を「四半期単位」で設計する
年間採用計画を12カ月で一括管理するのではなく、
「Qごとの採用目標・予算・チャネル」を設定することが重要です。
これにより、
- 採用効果を短期で検証できる
- 採用マーケットの変化に柔軟に対応できる
- 通年採用でもPDCAを高速で回せる
というメリットが得られます。
② 採用広報の常時発信
通年採用では、「常に見られている採用広報」が鍵です。
具体的には:
- 採用サイトを“動的”に更新
- SNS・YouTubeなどで社内のリアルを発信
- 季節・トレンドに合わせた採用キャンペーンの展開
ここで有効なのが 採用動画。
なかでも「体験入社動画」は、通年採用と非常に相性が良い施策です。
🎥 体験入社動画とは?
応募前に“働く一日”を疑似体験できる採用動画。
応募者が自分のキャリアを具体的にイメージしやすくなり、
通年採用における応募者の質とエンゲージメントを高めることができます。
▶ 体験入社動画サービスを見る
③ データドリブンな母集団管理
通年採用では、候補者データベースの活用が欠かせません。
採用管理ツール(ATS)やCRMを活用し、
- 候補者との接点履歴
- 興味度合い
- 選考進捗
などを一元管理することで、**「採用ナーチャリング」**を実現します。
通年採用では、応募から内定までの「長期接点」が多く発生します。
メール・LINE・動画メッセージを組み合わせた情報提供が有効です。
④ 内定者フォロー・育成の仕組みを整える
入社時期がバラバラでも、入社意欲を維持するためのフォローが必要です。
オンライン交流会・動画研修・メンター制度を整備し、
「入社前からチームの一員」と感じてもらえる環境づくりを行いましょう。
⑤ 採用KPIの見直し
通年採用では、年次単位の集計ではなく、**「継続的なKPI管理」**が求められます。
主な指標:
- 応募数・面接率・内定率(歩留まり)
- 採用単価(CPA)・採用スピード
- 入社後定着率・評価スコア
これらを月次または四半期で可視化し、戦略を継続的に最適化していきます。
通年採用の成功事例

事例①:IT企業(エンジニア通年採用)
プロジェクト単位で採用を行う仕組みを導入。
オンライン動画選考・体験入社コンテンツを組み合わせ、
通年で母集団形成と教育を同時に実現。
事例②:人材サービス業
新卒・第二新卒を対象に“いつでも応募できる採用ページ”を開設。
定期的に社員インタビュー・動画を更新し、応募率が安定的に維持。
事例③:飲食チェーン
全国店舗で常時採用を実施。
通年採用動画を活用し、エリア別・職種別の仕事内容を明示することで、
ミスマッチを抑制し採用効率を改善。
通年採用を支える仕組みとツール
|
カテゴリ |
ツール例 |
目的 |
|
ATS(採用管理) |
HERP Hire、HRMOS |
応募者情報・進捗管理 |
|
CRM(候補者管理) |
Sonar、Eight Career Design |
長期的な関係構築 |
|
動画採用ツール |
Taikennyusha、moovy |
採用ブランディング強化 |
|
タレントプール構築 |
MyRefer、TalentBase |
リファラル・ナーチャリング活用 |
これらを統合的に運用することで、**「年間採用の自動化」**に近づきます。
これからの通年採用の方向性(2025年以降)
1. AIマッチング・自動選考支援の進化
AIを活用したスクリーニング・マッチングツールの普及で、
年間通して候補者との最適マッチングが可能に。
2. 動画×通年採用の拡張
採用動画は、広報・説明会・内定フォローすべてに展開でき、
通年採用を支える重要な要素に。
応募前の理解促進から、内定後フォローまでを一貫して担います。
3. グローバル採用・リモート採用の増加
海外人材・地方人材をオンラインで採用し、
通年採用を「国境を越えた採用体制」へと進化させる動きも進んでいます。
まとめ|通年採用は「戦略的人材獲得」への第一歩
通年採用は、単なる採用スケジュールの変更ではなく、
**「経営と採用を接続する仕組み」**です。
成功の鍵は以下の5つです。
- 採用を年間設計として捉える
- 採用広報を常時発信する
- データとテクノロジーを活用する
- 教育・オンボーディングを仕組み化する
- 採用体験を最適化する
日本経済新聞・各種メディアに取り上げられた話題の採用動画サービス
